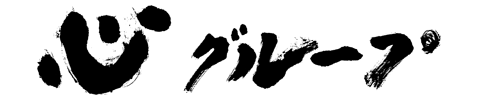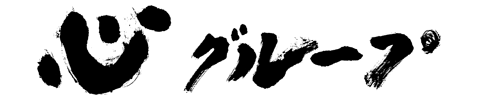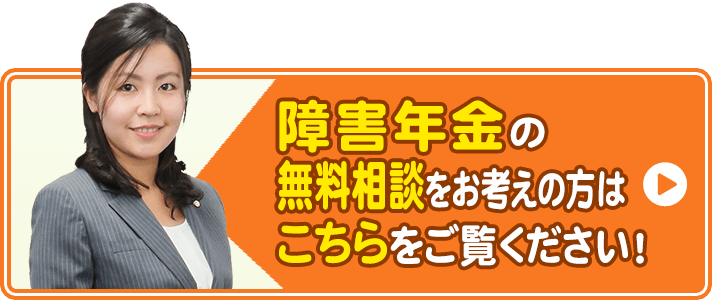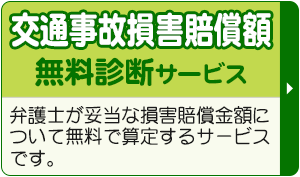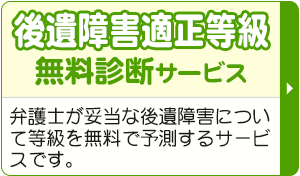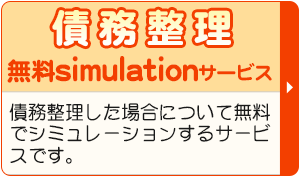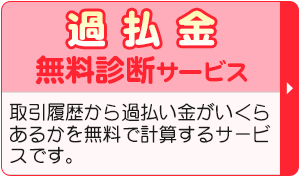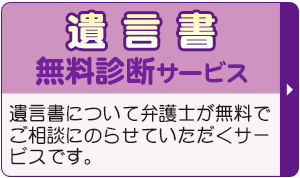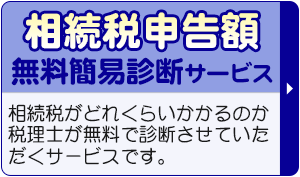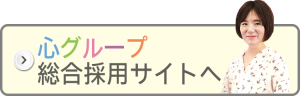障害年金の診断書に関するQ&A
Q障害年金の申請に必要な診断書とはどのようなものですか?
A
障害年金の申請には、原則として、日本年金機構が用意している所定の様式で、医師によって作成された診断書が必要となります。
様式は8つの種類に分かれており、障害の状態を審査側に最も伝えやすい様式の診断書を選び、医師に作成してもらいます。
例えば、人工関節置換術を受けたという方は「肢体の障害用」の診断書を選び、うつ病の方は「精神の障害用」の診断書を選ぶこととなります。
Qなぜ診断書が重要なのでしょうか?
A
障害年金の審査は、申請者と個別に面談等するわけではなく、書面のみで行われます。
また、障害年金の認定基準は、主に医学的な見地から障害の程度を認定する仕組みになっています。
そのため、医療の専門家である医師が、直接申請者の症状を診察し、医学的な見地から作成した診断書は、障害の状態を審査するに際して最も重要な書類となっています。
診断書の様式に設けられている記載項目は、認定基準を反映したものになっており、これらの項目に実際に記載された内容を認定基準に当てはめることで、審査が行われます。
そのため、これらの項目が実態を反映した内容になっている必要があります。
例えば、精神の障害用の診断書には、「適切な食事」「身辺の清潔保持」等の日常生活の状況について、「できる」から「助言や指導してもできない若しくは行わない」までの4段階で評価をする項目がありますが、この項目の評価を適切にしてもらえないと、適切な審査を受けることが難しくなってしまいます。
肢体の障害用の診断書についても、同様に「つまむ」「片足で立つ」等の日常生活における動作について、「一人でうまくできる」から「一人で全くできない」までの4段階で評価する項目があります。
これらのように、検査数値ではないものについては、特に主治医に現在の病状をしっかり伝え、診察してもらい、適切に診断書に反映してもらうことが重要となってきます。
Q診断書はどの医療機関に作成を依頼すればよいですか?
A
障害認定日(原則として初診日の1年6か月後)時点の診断書は、障害認定日当時に受診していた医療機関に診断書の作成を依頼します。
その際は、障害認定日から3か月以内の期間の症状を記載した診断書が必要です(20歳前より前に初診日がある障害基礎年金の申請で、20歳になった時点が障害認定日となる場合には、20歳の誕生日の前後3か月の期間の症状を記載した診断書が必要とされます)。
たまたま障害認定日から3か月の期間中に転院した場合には、転院の前後どちらの医療機関にもカルテが残っている可能性があり、どちらの医療機関にも診断書の作成を依頼することが可能です。
申請時点の診断書は、現在の通院している医療機関に作成を依頼します。
この場合には、申請日前3か月以内の症状を記載した診断書が必要です。
診断書の作成を依頼したその日に診察も受けた場合には、依頼した日時点での症状が記載されることになるでしょう。
医療機関の窓口で診断書の作成を依頼し、診察を受けずに診断書を作成してもらった場合には、診断書の作成を依頼した時の直前の受診日時点での症状が記載されることになるでしょう。