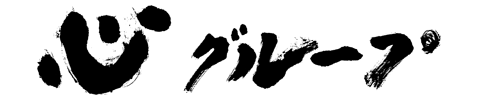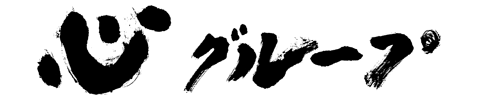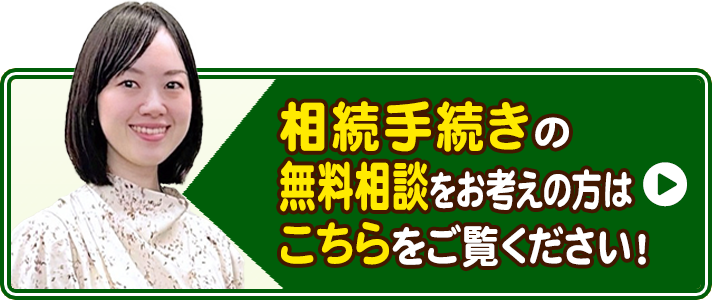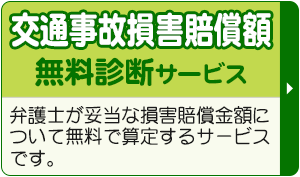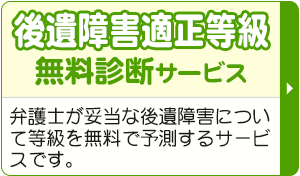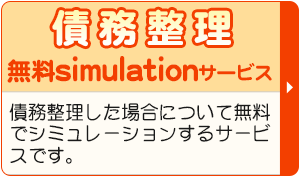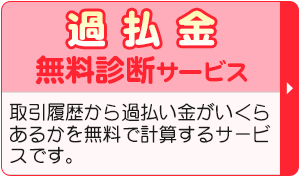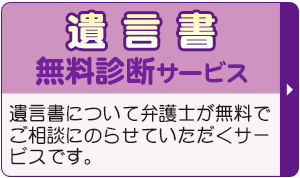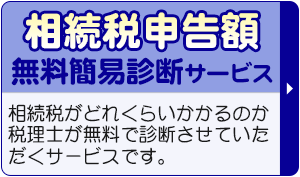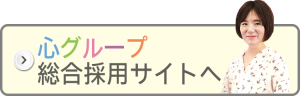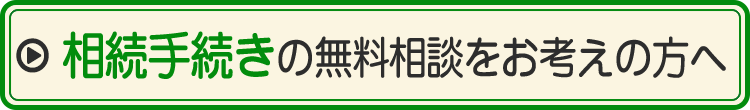亡くなった人の預金が少額の場合でも相続手続きは必要か
1 基本的には相続手続きをするべきであるといえます
人が亡くなると、その方の名義で所有していた財産は相続財産となり、基本的には法定相続人に承継されます。
預金もその対象であり、たとえ預金口座内に入っている金額が少額であっても、法律上は相続財産に含まれます。
そのため、原則としては、口座内の金額にかかわらず、亡くなった人の銀行口座についても相続手続きを行うべきであるといえます。
相続が開始した(被相続人が亡くなった)事実が金融機関に伝わると、通常であれば預金口座は凍結され、入出金ができなくなります。
これは、口座内の預金が不正に流出することを防ぎ、遺産分割におけるトラブルを予防する効果もある措置です。
そのため、残高が数百~数千円といった金額であっても、金銭を引き出すことはできません。
預金を動かすためには、相続人の調査、遺産分割協議、そして金融機関での解約・払戻手続きといった一連の作業を行う必要があります。
被相続人名義のまま口座を放置しておくことは、後々の管理負担の増加やトラブルにつながる可能性がないとはいえません。
したがって、金額の多少にかかわらず、銀行口座の相続手続きは原則として行っておく方が安心といえます。
2 罰則はないが預金保険機構の管理に移されることがある
もっとも、少額の預金が入っている口座について、相続手続きを行わずに放置したとしても、法律違反になるわけではありません。
預金を解約しないままでいても罰則が科されることはなく、法的に強制されるものではないのです。
そのため、残高が数百円や数千円である場合、手間がかかるという理由によって相続手続きをしないままでいるケースも見受けられます。
しかし、まったく動きがないまま放置され続けている預金は休眠預金となり、一定の期間を経過した後に金融機関から預金保険機構に移管される制度が存在します。
例えば10年以上取引のない口座は、金融機関において休眠預金として扱われ、最終的には国の管理に移ることになります。
移管された後であっても、相続人が請求することで払い戻しを受けることは可能ですが、そのためには預金保険機構を通じた手続きが必要になり、労力的な負担が増える場合があります。
また、口座を放置したままであると、金融機関側から相続人に対して照会がなされる可能性もあり、そのたびに連絡などをせざるを得なくなるということも考えられます。
したがって、法的な罰則はないものの、長期的な視点で考えた場合、被相続人の口座を放置することは得策ではないといえます。
3 休眠預金等活用法に基づく預金の扱い
2018年に施行された民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(通称、休眠預金等活用法)により、金融機関で10年以上入出金取引がない預金は休眠預金とされ、預金保険機構に移されることになりました。
移された預金は、その後指定活用団体に交付され、公益活動等のための資金として活用されることになります。
たとえば、子どもや若者の貧困対策や災害支援、地域活性化などに用いられます。
この制度により、相続手続きをせずに被相続人の口座を長年放置しておくと、預金が社会のために使われるという流れになります。
もちろん、相続人からの請求があれば、休眠預金になった後であっても払い戻しを受けることは可能です。
ただし、その際には相続関係を証明する書類(戸籍謄本、相続人全員の同意書、遺産分割協議書など)や、金融機関所定の書類を作成して提出する必要があります。
実質的には、相続手続きを省略することはできないということになります。
被相続人の口座内の預金が金融機関に残っているうちに相続手続きを行えば比較的スムーズに払い戻しを受けられますが、休眠預金になり預金保険機構に移管された後になると、関与する機関が増えることから、払い戻しに要する時間や手間が増えることが予想されます。
このような事情から、亡くなった人の口座は少額だから放置するというのではなく、少額だからこそ早めに整理しておく方が合理的であるといえます。