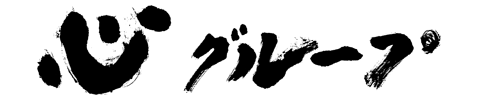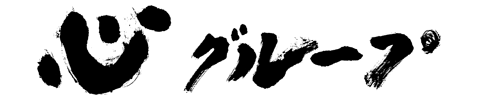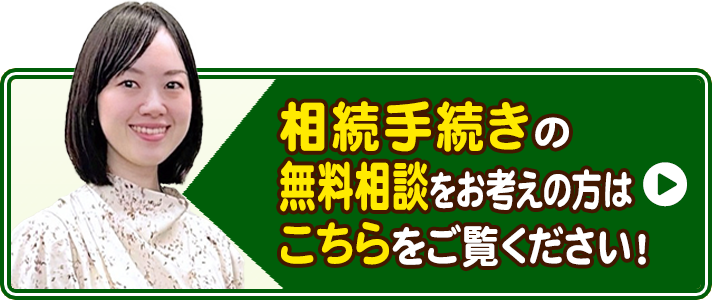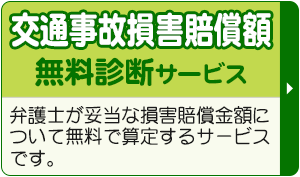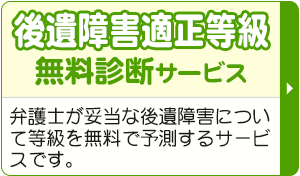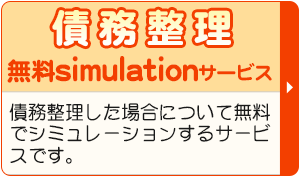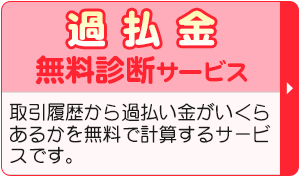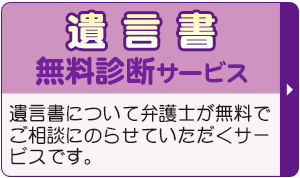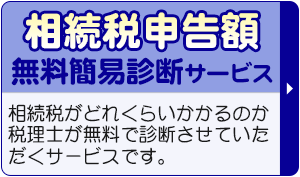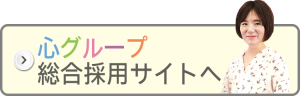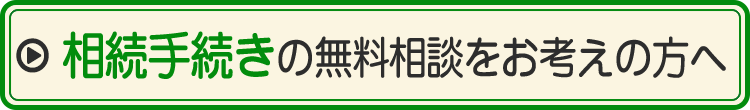相続手続きの期限
1 期限が存在する相続手続きについて
相続手続きには様々なものがありますが、そのなかには、法律で期限が定められているものが複数存在します。
代表的なものとしては、不動産の相続登記と相続税申告が挙げられます。
これらを期限内に行わない場合、過料や税の加算などのペナルティが課せられるおそれがあります。
さらに注意しなければならないのは、不動産の相続登記や相続税の申告をするための前提となる作業も存在するという点です。
このような作業も考慮したうえで、スケジュールを組まなければなりません。
2 前提として必要となる作業について
相続手続きをする前提として、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議(遺産分割協議書の作成)を行う必要があります。
相続人の調査をするためには、基本的に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を取得します。
漏れがあると、遺産分割協議が無効になってしまうので、相続人の調査はとても重要な作業になります。
並行して相続財産の調査も行います。
遺産分割協議や相続税の申告のためには、被相続人の不動産、預貯金、有価証券、債務などを正確に把握しなければなりません。
相続人と相続財産の調査を終えたら、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意内容を記載した遺産分割協議書を作成します。
実務においては、遺産分割協議書には相続人全員が署名と押印をし、押印には実印を用いて印鑑証明書も添付します。
3 相続登記の期限について
令和6年4月から、不動産の相続登記が義務化されています。
基本的には、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
期限内に相続登記をしなかった場合、正当な理由がない限り、過料が科される可能性があります。
また、相続登記をしないと、売却や担保権の設定ができないことや、次の相続が発生した際に相続人が増えて権利関係が複雑になるなど、事実面における問題も発生してしまいます。