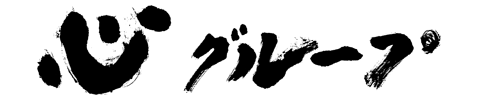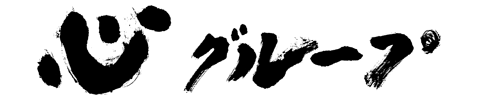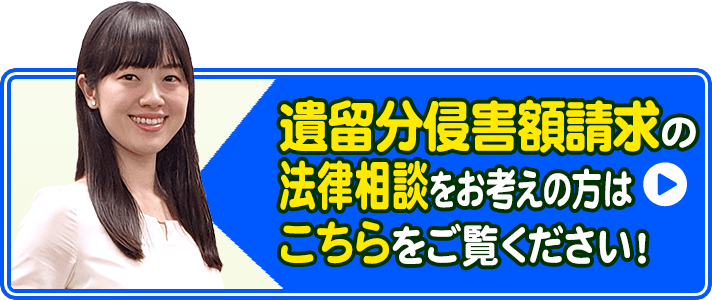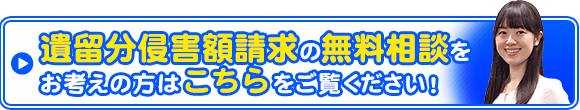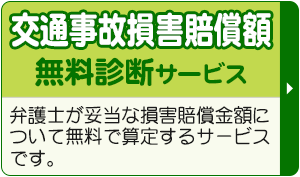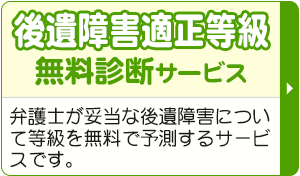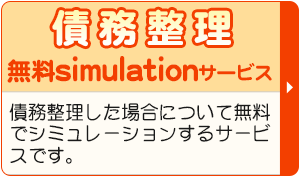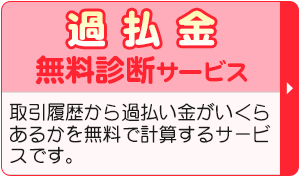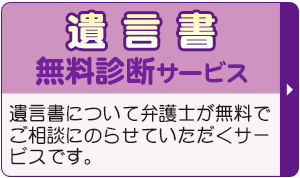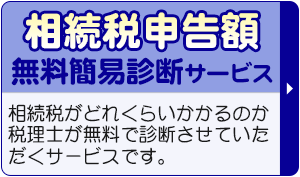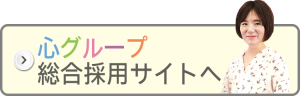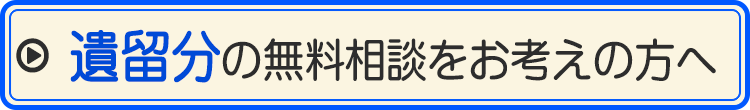遺留分侵害額請求の消滅時効はいつまでか
1 相続の開始又は遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき 2 相続開始から10年を経過したとき 3 請求後も消滅時効が成立する場合がある(上記1の補足) 4 遺留分侵害額請求については、弁護士にご相談を
1 相続の開始又は遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときに、時効により消滅します(民法1048条前段)。
これは、法律関係の早期安定の要請に基づくもので、遺留分権利者の主観によって定められた期間になります。
1年という短い期間によって、消滅してしまうので、注意が必要です。
この消滅時効の期限について時計の針は進む条件となっている「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、基本的に、単に相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈の存在を知っただけでなく、その贈与や遺贈が遺留分を侵害していることを知る必要があります。
2 相続開始から10年を経過したとき
上記1の遺留分権利者毎に異なるもののほかに、遺留分侵害額請求権は、相続開始時から10年を経過することで消滅します(民法1048条後段)。
これは、相続関係に基づく権利変動については、短期に決着をつけることによって法律関係の確定や取引の保護を図る趣旨と考えられています。
また、こちらの機関については、除斥期間であると、一般的には考えられています。
そのため、上記1の消滅時効のように時効を主張する者から時効を援用する意思表示がなくとも、当然に時効により消滅すると考えられています。
3 請求後も消滅時効が成立する場合がある(上記1の補足)
上記1の「1年の消滅時効」について対象となるのは、遺留分が侵害されたことを理由に、その侵害分の補填を金銭的に請求(金銭給付)する意思表示ができる権利のことです。
つまり、1年の期間内に遺留分侵害額請求の意思表示をした結果、遺留分権利者の金銭給付請求権は、当該1年の期間とは関係がなくなります。
一方で、遺留分侵害額請求の意思表示をした結果として生じた金銭給付請求権については、別途債権として消滅時効が生じる場合があります。
金銭給付請求権の消滅時効は、意思表示をしたときから5年ですので、遺留分侵害額の請求をする意思表示をしてから、5年の間に請求権を行使しない場合は、消滅時効により消滅してしまう場合があります。
「1年」という期間は知っていて、遺留分侵害分の請求をする意思表をした後、5年以上放置してしまい、請求できなくなる、というトラブルが生じることがあるので、遺留分侵害額請求の手続きを行う場合は、期間の意識が常に必要となります。