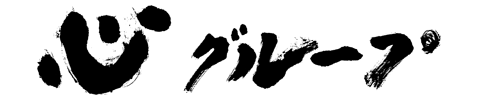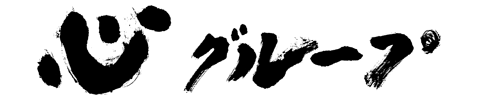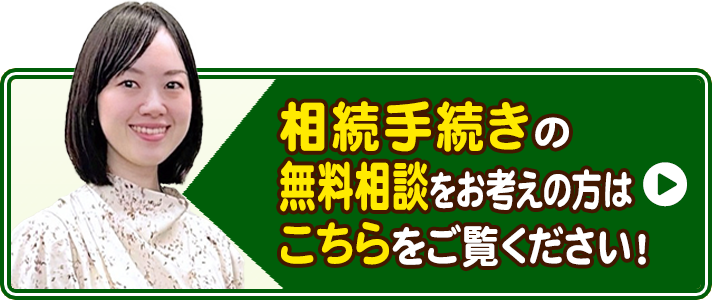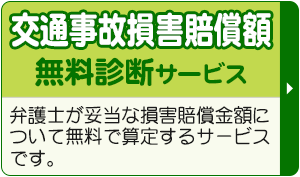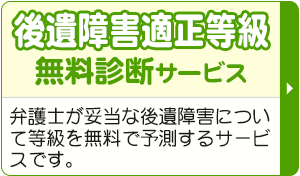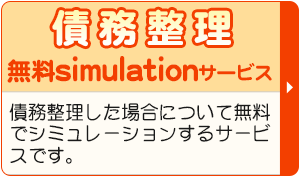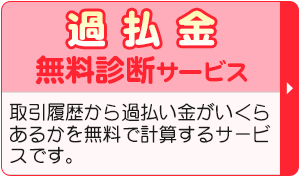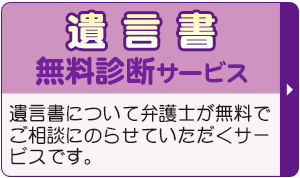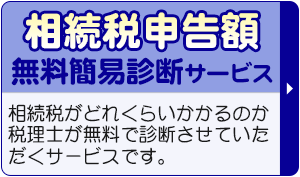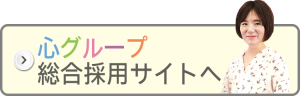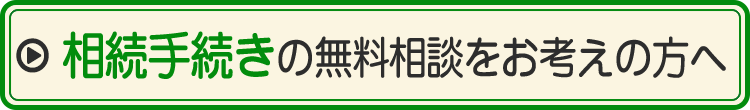戸籍謄本と除籍謄本の違いやそれぞれが必要な場面
1 戸籍謄本と除籍謄本の違いについて
戸籍謄本は、現在生存している方が1人でもいる戸籍の、すべての記載内容(筆頭者およびその戸籍に入っている方全員)を写したものです。
例えば、現在の本籍地にある家族全員の氏名、生年月日、続柄、出生、婚姻、死亡などの情報が記載されています。
これに対して、除籍謄本は、その戸籍に記載されていたすべての人が、死亡、婚姻、転籍などの理由で戸籍から除かれ、戸籍自体が空(から)になったものです。
見た目は戸籍謄本と似ていますが、記載されている人物がすべて除籍済みであるという点で異なります。
2 被相続人の除籍謄本が必要となる場面
遺産分割協議や相続手続きをするための前提として、被相続人(お亡くなりなられた方)の相続人を確定させる必要があります。
その際、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて取得する必要があります。
被相続人がかつて入っていた戸籍が、婚姻や転籍により複数存在することが多いため、そのような場合には時系列を遡ってすべて集める必要があります。
例えば、被相続人が婚姻して元の戸籍(一般的には親の戸籍)から抜けていた場合、被相続人の最後の戸籍(他に戸籍に入っている方がいなければ除籍謄本になります)に記載された従前の本籍地を参照し、元の戸籍謄本を取得します。
元の戸籍から両親や兄弟などすべての方が抜けている場合には、元の戸籍は除籍謄本になります。