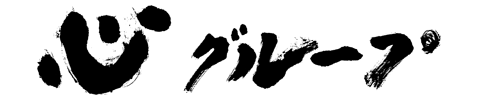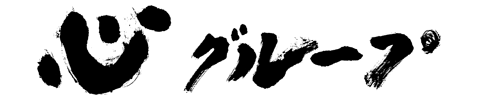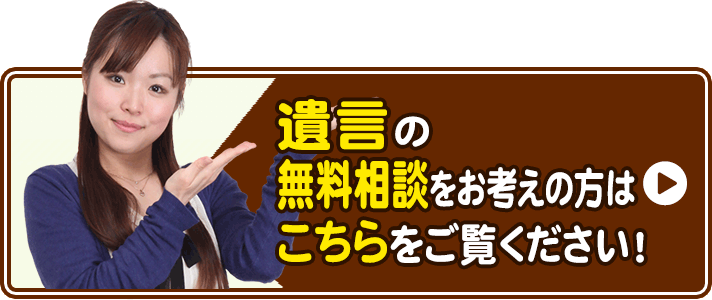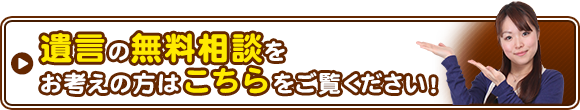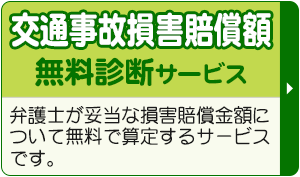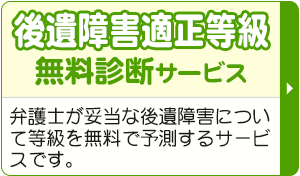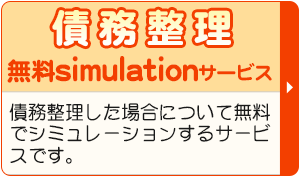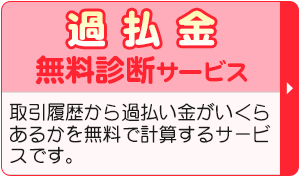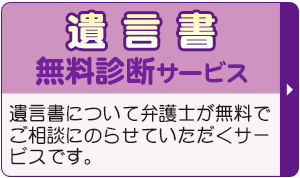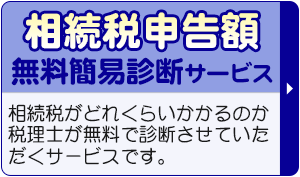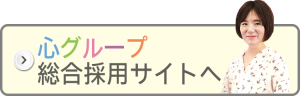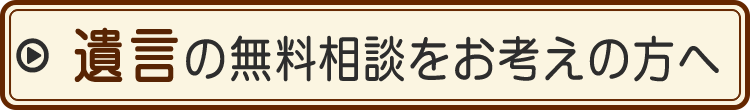遺言の検認手続きの流れと必要書類
1 検認手続きの流れ
遺言書を発見した相続人が、必要な書類を集め、家庭裁判所へ検認の申立てをします。
その後、裁判所から、相続人の全員に検認期日が郵便で通知されます。
申立てした人が、相続人全員の現住所を特定できない場合には、当然ですが、通知は届かず、裁判所に返送されます。
遠くに住んでいたり、疎遠だったり、理由はいろいろですが、他の相続人全員の今の住所まで特定できないことは、ありがちです。
相続人は、その検認期日に出席します。
裁判所は役所ですので、検認期日は平日の日中です。
検認期日には、裁判官、裁判所書記官と相続人全員がいます。
遺言書が入っている封筒を開け、遺言書の内容を確認します。
相続人全員に、遺言書の筆跡が遺言者の筆跡か確認されます。
また、遺言書のハンコと封筒の封印が遺言者のハンコかも確認されます。
間違いないとか、多分そうだと思うとか、わかりませんとか、思ったとおり回答します。
検認期日のやり取り、遺言書コピー、封筒コピーは、検認期日調書という形になり、後日、裁判所から郵便で届きます。
2 必要書類
⑴ 申立書
裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
⑵ 添付書類
ア 基本
①遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本
②相続人全員の戸籍謄本
③遺言者の子が死亡している場合、その子の戸籍謄本
イ 相続人が遺言者の父母・祖父母等の場合
④遺言者の直系尊属が死亡している場合その記載ある戸籍謄本
ウ 相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合
④遺言者の父母の出生時から死亡時までの戸籍謄本
⑤遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
⑥遺言者の兄弟姉妹が死亡している場合、その戸籍謄本
⑦代襲者としてのおいめいが死亡の場合、その記載ある戸籍謄本
⑶ 収入印紙
800円分の収入印紙も必要です。
組合せは決まっていません。
裁判所内の売店で売られていることもありますが、売店がない裁判所も多いです。
⑷ 郵便切手
裁判所と相続人の連絡は郵便のため、あらかじめ、それに必要な郵便切手を納め、不足した追加で納め、余れば戻って来ます。
収入印紙と違い、何十何円切手が何枚など、組み合わせが、管轄する家庭裁判所ごとに、細かく、決められています。
収入印紙と同じく、裁判所内の売店で売られていることもありますが、売店がない裁判所も多いです。